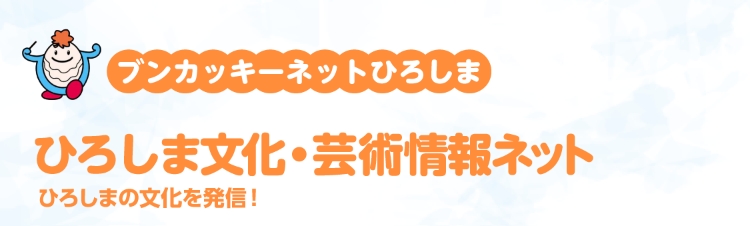本と共に歩む—「ひろしまブックフェス」が描く未来へ続くページ

ひろしまゲートパーク内で「第2回ひろしまブックフェス」が開催されます。出版業界の現状を打破し、書店や出版社が一丸となり挑戦する新しい出版と本屋の在り方とは? 主催の財津正人さんと実行委員長の三浦明子さんに、同フェスの魅力や本を取り巻く現状と未来について聞きました。
<プロフィール>
財津正人
株式会社本分社代表取締役
大阪で出版取次会社に勤めたのち、書店を開業。紆余曲折を経て広島で同社を設立し、地域に密着した出版活動を展開。2009年から「ブックスひろしま」を主催し、本を取り巻く地域の文化振興にも力を入れる。2024年、「ひろしまブックフェス」を立ち上げ、業界の活性化を目指す。
三浦明子
ジュンク堂書店広島駅前店店長
1999年4月、ジュンク堂広島駅前店開店同時に入社。書店員の枠を超え、中国新聞で本や書店に関するコラムを掲載する他、テレビやラジオでも本の紹介を行う。本と絡めたイベントを多数行ってきた経験を活かし、2024年開催の「第1回ひろしまブックフェス」より実行委員長を務める。
多彩な出店者と個性が光る本の祭典「ひろしまブックフェス」

――「ひろしまブックフェス」の内容、立ち上げのきっかけについて教えてください。
財津:出版社、新刊書店、古書店、取次が一同に集まる本の祭典です。2024年に開いた第1回目は、約30店が出店し、100台のワゴンで古本やアウトレットブックのほか、新刊書籍を販売しました。10日間で1万人以上が訪れ盛況でした。
出版業界は長く低迷し、市場も縮小し続けています。本に携わる人々は、「このままではいけない」とここ何年もやり方や切り口を変え、トライアンドエラーを繰り返してきました。これまで僕は「ブックスひろしま」という名前で、2009年から作家トークショーや古本市などのイベントを催してきました。それが進化した形が「ひろしまブックフェス」です。2025年はさらにパワーアップし、「立ち呑みブックス」も合わせて開催する予定です。

――同フェスの一番の魅力は何だと思いますか?
三浦:出店者それぞれが強く特徴を出しているところです。例えば、普段新刊書店に行っても、どこも同じようなラインナップになりがちですが、ここでは各書店が個性や理念を掲げ、独自の本をセレクトしています。お客さまは書店員と直接話をして、触れ合いながら本を選ぶことができ、普段は手に取らないような1冊に出会えるかもしれません。書店員にとっても、トークスキルや選書力が問われる場です。書店員とお客さまが一緒に創り上げる新しい本屋のカタチが、このフェスでは実現されています。
――1回目は来場者数、売上とともに十分な記録を達成し成功をおさめました。
財津:来場者数や出展者の反応から、これだけ多くの人々が本を求めて集まってくれるんだという手ごたえを感じました。特に、本を並べているだけでなく、書店や出版社が自ら接客することで、違いが生まれました。ある出版社のブースでは、ワゴンの横に立ってお客さまと話をしたところ、驚くほど本が売れたんです。本を通しての対話の面白さを、来場者も出展者も再確認した10日間でした。

三浦:新刊書店員として、今一番必要なのは「自分たちは接客業だ」という意識だと思います。本をただ並べる時代は終わり、お客さまと直接対話して本を売ることの喜びは、書店員にとって大きな財産となります。その体験は、ネット書店では味わえない嬉しさをお客さまにも提供できるのです。
震災と原爆をテーマにした特別企画と新たな試み「立ち呑みブックス」
――イベント内フェアとして「阪神大震災30年、広島被爆80年」を企画されていますね。
財津:各店がセレクトした震災や原爆に関連する本を集め、1つのブースとして展開します。新刊と古本を合わせ、約300冊が並ぶ予定です。今回、「圧倒的な現実に想像力で立ち向かう」をイベントテーマに掲げています。最近の日本や世界の情勢を見てください。相も変わらず戦争をし、人は分断され、差別が蔓延。さらに自然災害が頻繁に発生しています。私たちは、常に「圧倒的な現実」に直面しながら生活しているのです。その現実にどう立ち向かうか、どう受け止めるかを学ぶために、過去の出来事を知り、未来に思いを馳せることが重要だと考えています。今回のフェアは、そんな本を多くの方に知っていただきたく、企画しました。

――日本酒を楽しめる「立ち呑みブックス」も同時開催されます。
財津:日本酒を楽しめるブースを、エリア内に設けます。購入した本を持ち込んで、ぜひお酒と一緒に楽しんでもらいたいです。発端は、2024年の8月と11月、紙屋町シャレオの一画で古本屋と立ち呑み屋を合体した期間限定のお店「立ち呑みブックス」を開いたことです。僕は日本酒が好きでよく飲むんですが、「日本酒と本は相性がいい」と長年思っていました。日本酒好きな人は、物事をじっくり思考する人が多いと感じています。

三浦:実際、私も店頭に立ちましたが、酒も本も好きな人がたくさん集まりました。お燗をチビチビ飲みながら黙々と本を読む人、本好きという共通項から隣同士で話し始める人、カウンターに立つ人と映画や本の話で盛り上がる人、楽しみ方はそれぞれでした。自由度の高さが評判を呼んだと思います。
財津:日本酒業界と出版業界は酷似していると思っています。どちらも市場が縮小し、活性化のために必死で生き残りをかけています。2024年に日本の「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されたこともあり、日本の伝統産業と日本酒の奥深さを味わってもらいたいと思います。4月は花冷えの時期です。お燗をおすすめしますよ。
連携しながら前へ進む広島の本屋と書店員の未来

――本、そして本屋に未来はあるのでしょうか?
財津:「本が売れない時代」といわれていますが、実際は違います。出版業界は不況ですが、読書不況ではありません。読書をする層はしっかりといます。書店で本を買う機会が少なくなっただけです。本を読む人々は確かに存在しており、それが僕たちの希望です。
三浦:エンターテインメントの幅が広がり、映画や音楽、ネットなど、時間の過ごし方に選択肢が増えました。さらに、サブスクの登場で娯楽の楽しみ方が多様化しています。これと同じように、本もネットや電子書籍で購入されることが増え、町の本屋さんが減少する中で、古書店や独立系書店は増加傾向にあります。本が全く売れていないわけではありません。読書している人は依然として多いのです。

―その読者層の心を捕まえるために、そして本屋が存続するためにできることは何でしょうか?
三浦:書店員として、「この本いいですよ」と紹介することはもちろん大事です。しかし、本が売れるだけでは足りません。お客さまに「ぜひこの店で買いたい」と思わせることが必要です。何度も繰り返しますが、本屋が生き残るために、待っているだけではもうダメです。変化を恐れず、柔軟性を持って動いていけるかどうかが重要です。私は、全ての本屋が生き残ってほしいと強く願っています。競争ではなく、共存を目指さなければなりません。広島は書店員同士の横の繋がりが強いといわれています。それが、地方の良さかもしれません。首都圏ではできないけれど、程よくコンパクトな広島だからできることがあります。
文化の集積地をつくり広島の文化シーンをより豊かに

――期待が持てますね。このイベントを、どう発展させていきますか?
三浦:何事も継続することが大事だと思っています。そのためには、今後も何かしらの変化をつけていかなくてはなりません。今回でいうと、日本酒が加わりました。私の最終目標は、本、音楽、美術、スポーツなどが一堂に会した、文化的価値の底上げイベントです。広島は、若者の転出超過が進んでいると聞きます。理由のひとつに、エンタメが少ない点が挙げられています。だったら、広島の中から自分たちで生み出していけばいいんです。住んでいる人間も楽しいと思える場所じゃないと、魅力増加には繋がりません。
財津:広島は、街のサイズも市場も「ちょうどいい」と思っています。小規模な都市だと、何をやっても目立ちすぎるやりにくさがあります。逆に東京、大阪は、規模が大きすぎて何をやっても目立ちづらいんです。広島だと、大勝負をかけずとも、ある程度の頑張りで成せることが多いと思います。三浦さんが話す総合文化イベントは、例えばオリンピックのように4年に1回のペースで、本当に実現できる可能性があります。広島の本屋さんと僕たち出版社が協力し合えば、大きなイベントの開催、そして本業界のV字回復も夢ではありません。

――お二人から、広島への愛を強く感じます。
財津:30年前、関西から来た僕を受け入れてくれた広島の出版業界に、何かしらの形で、恩を返せたら……という思いがあります。この街で、楽しいと思えることを続けていきたいです。結果それが、皆さんの「楽しい」に繋がっていけば嬉しいですね。
三浦:私も同じく、書店員としての自分は広島が育ててくれたと思っています。ラジオに出させてもらえばリスナーさんから応援があり、SNS発信を見てファンになってくれる方も。書店業界のみならず、広島という街に恩返しをしていきたいです。皆さんと一緒に楽しいことができたら最高です。
ひろしまブックフェス
日時
2025/4/4(金)~4/10(木)10:00~19:00
場所
ひろしまゲートパーク 内 大屋根広場(旧広島市民球場跡地)
取材・文/大須賀あい 撮影/岸副正樹
取材場所/古本と珈琲 楢